HISTORY
節辰の歴史
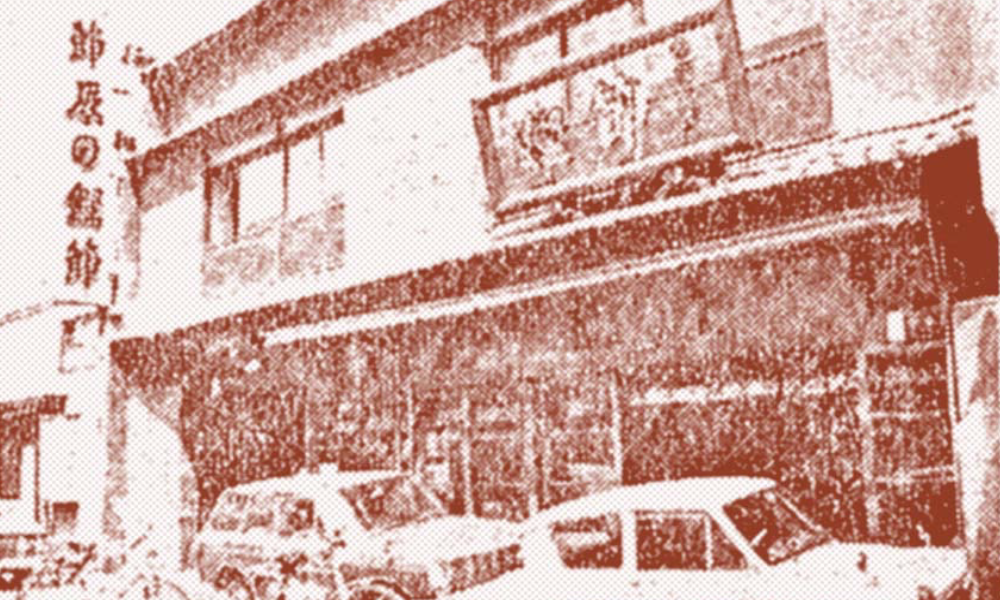
彦兵衛と辰蔵
創業は江戸末期の安政元年(1854年)。ここ名古屋の地で商人 大野屋彦兵衛が海産物の乾物商を開いたのが始まりです。彦兵衛の養子 勝田辰蔵が二代目となり、屋号を節辰(フシタツ)と定めて鰹節専門のお店を構えます。そこから170年。六代目となった今も、同じ土地、同じ屋号で商いを続けています。今に続く「節辰商店」の名前は、この勝田辰蔵に由来します。

名古屋有数の卸問屋
節辰の商いは人々の暮らしとともにあります。明治大正期、三代目の吉次郎は顧客嗜好に合わせた配合だしを地域のそば/うどん屋さんに卸す小売業で発展。昭和初期には名古屋有数の卸問屋となりました。
昭和20年、大空襲で名古屋は焼け野原となり、節辰も一時休業。しかしながら戦後復興とともに事業を再開。高度成長期(昭和41年)には、本物の味を手間をかけずに味わえる「だしパック」を開発。製造メーカーとして歩み始めます。そして日本が経済大国となった昭和後期、五代目の吉雄は高級食材を外国から仕入れる輸入業に参入し、節辰は総合食品商社として発展しました。

在庫の鰹 七千本焼失
昭和49年には本社工場が全焼。在庫の鰹七千本を焼失するも、同年に新社屋を完成させて事業を継続。平成7年には、新たにめんつゆ工場を建設し、現在のキャッチフレーズでもある「節、だし、めんつゆ」の製造メーカーとなりました。
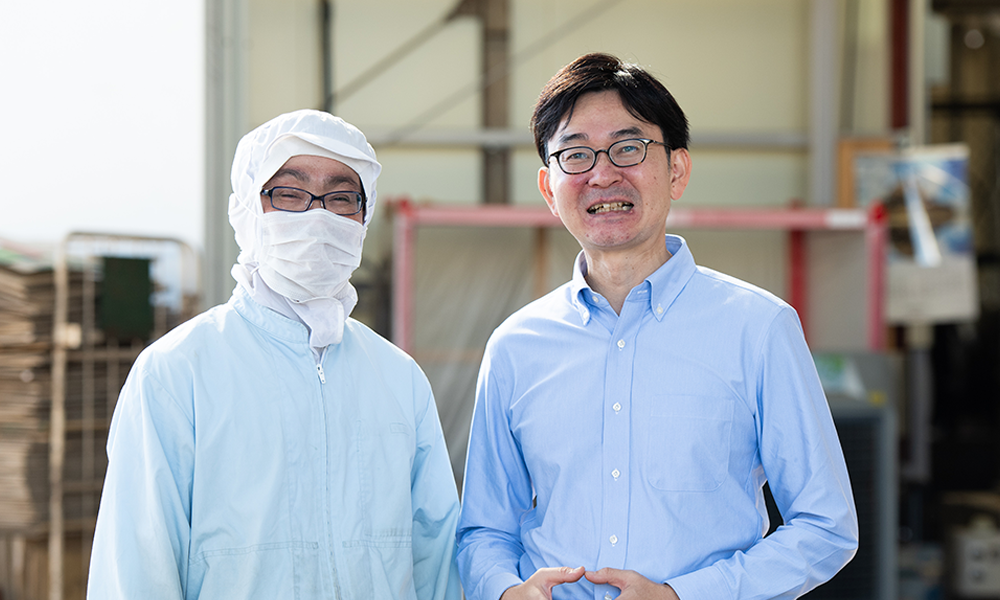
当たり前を続けること
長い歴史の通り、節辰は「長期的な信頼関係」を大切にしています。得意先さま、仕入先さまとの永続的な取引が、何より「品質向上」に寄与します。嘘をつかない。ごまかさない。真面目に取り組む。適正な値をつける。言葉にすると当たり前ですが、その当たり前を、どんな時代もちゃんと続けていくこと。これからも、地に足のついた商売を続け、人々の暮らしとともにある会社でありたいと思います。




